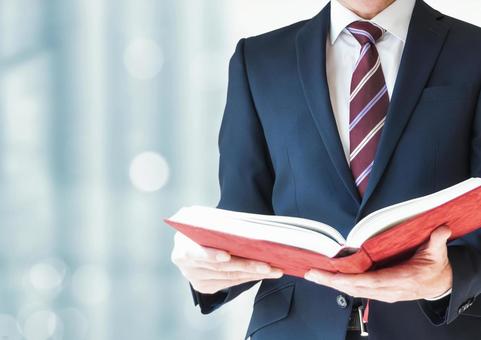1 後遺障害とは
後遺障害とは、交通事故などによって傷病を受け、治療後も事故前の状態にまで完全に回復せず、不具合として後遺症が残ってしまうことがあります。
交通事故においては、交通事故によって生じてしまった後遺症のうち、自動車損害賠償保障法に基づく「後遺障害等級」のいずれかに該当したものを「後遺障害」といいます。
2 後遺障害の等級認定について
(1) 後遺障害等級は、損害保険料率算出機構という審査機関で審査され、基準を満たすときには、後遺障害等級の認定がなされます。
(2) 後遺障害は、その症状の重さに応じて1級から14級までの等級が定められています。
この等級のことを後遺障害等級といい、等級の数字が小さくなるほど後遺障害は重くなります。
後遺障害等級を認定しているのは「損害保険料率算出機構」という機関です。
3 後遺障害等級の申請方法について
後遺障害等級認定を受けるための基本的な流れは以下のとおりです。
(1) 医師から症状固定の診断を受ける。
症状固定とは、症状が一進一退となり、これ以上は治療を続けても良くも悪くもならないと判断される状態のことです。
(2) 医師に後遺障害診断書の作成を依頼する。
「後遺障害診断書」は後遺障害等級認定に必ず必要となります。
後遺障害診断書には、主治医により、被害者の身体のどの部位に、どの程度の症状があるのかなどを詳細に記載してもらいます。
(3) 申請書類一式を提出する(2通りの方法あり)
① 事前認定
加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出し、その他書類は任意保険に用意してもらいます。
② 被害者請求
加害者側の自賠責保険会社に被害者自身で必要な書類を提出する
申請方法は自由に選べますが、適切な等級に認定される可能性を高めたいのであれば被害者請求をお勧めします。
(4) 審査機関で審査が行われる
(5) 後遺障害等級認定の結果が通知される
4 後遺障害等級の認定結果に納得できない場合
後遺障害等級認定の結果に納得できない場合は、異議申立てをすることができます。
異議申立ての審査は、初回の申請時の審査以上に、客観的・専門的な審査がなされるため、多くの場合手続に2ヶ月~6ヶ月程度必要となります。
異議申立てのため、医学意見書などを準備して申請することが多いです。
5 弁護士ができること
交通事故後の後遺障害等級認定は、被害者が事故によって受けた傷害の程度に基づき、後遺障害の等級を決定する重要な手続きです。この認定が確定することで、慰謝料や逸失利益など損害賠償額が大きく変わるため、適正な等級認定を受けることは非常に重要です。
弁護士ができることは、主に次のとおりです。
(1) 後遺障害等級認定のサポート
後遺障害等級認定を申請する際に、必要な書類や証拠を整え、手続きの代理を行います。例えば、医師の診断書や治療記録、事故の状況証明などを精査して申請することなどです。
(2) 医師との連携
後遺障害等級認定には医師の診断書が重要な役割を果たします。
弁護士は適切な医療証拠が集まるようにサポートします。
必要な場合には、後遺障害の認定基準に沿った診断書作成を主治医に依頼することもあります。
(3) 適切な等級を求めるためのアドバイス
後遺障害等級は、事故後の障害の程度を評価するもので、等級が高いほど賠償金額も増えるため、弁護士はその判断基準を理解し、適切に認定を受けるためのアドバイスを行います。
(4) 医療証拠の整備
後遺障害等級認定のためには、診断書や治療記録に加えて、事故と後遺障害との因果関係を証明できる証拠が求められることがあります。
弁護士は必要に応じて専門医の意見を求めたり、証拠を集めたりします。
(5) 認定結果に対する異議申立て
もし後遺障害等級認定の結果が納得いかない場合、弁護士は異議申立てを行うサポートをします。
後遺障害の程度が低く評価されたと感じた場合、専門医の意見書を追加で提出したり、再度の審査を求めることができます。
(6) 示談交渉や裁判でのサポート
後遺障害等級が確定すると、その等級に基づいて賠償金が算定されます。
弁護士はその賠償金額が適正であるかどうかを評価し、相手方保険会社と交渉を行います。
もし交渉で和解が成立しない場合は、訴訟を提起し、適正な損害賠償金を請求します。
(7) 弁護士は、交通事故による後遺障害等級認定において、申請手続き、証拠の整備、異議申立てのサポート、賠償金交渉など、さまざまな場面で被害者を支援します。
後遺障害等級が正しく認定されることは、その後の賠償金に大きな影響を与えるため、専門的なサポートが重要です。
まずは、当事務所にご相談ください。