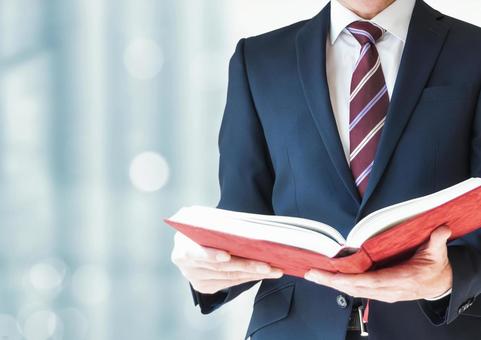
1 症状固定とは?
(1) 交通事故による損害として認められる治療関係費は、原則として「症状固定日」までの各費用をいいます。
交通事故では、損害賠償額を算定する上で、重要なキーワードです。
(2) 症状固定とは、「これ以上治療しても症状が改善しない、もとの状態に戻らない」状態を言います。
(3) むちうち症を例にすると、病院で投薬やリハビリを受けると少しよくなるけれど、少し経つとまた戻り、という一進一退を繰り返す状態が症状固定です。
2 症状固定時期と賠償額の関係について
(1) 症状固定により治療期間は終了します。
原則として、症状固定日までの医療関係費が事故による損害となります。
症状固定日後も残存する症状については、後遺障害として損害賠償の対象となります。
(2) 症状固定後は、後遺障害等級認定を受けて、後遺障害が認定されれば、逸失利益や後遺障害慰謝料を請求できるようになります。
3 症状固定について知っておきたいポイント
(1) では、「症状固定」を決めるのは誰でしょうか?保険会社が勝手に決めてよいことなのでしょうか?
保険会社から「そろそろ症状固定してください」と言われ、後遺障害診断書が送られてきたり、突然に「治療費を打ち切ります」と言われるケースがよくあります。
(2) しかし、保険会社は医師ではなく、医学的判断を行うことはできません。
症状固定は、被害者自身と症状経過を見てきた医師が判断するべきことがらです。
そして、裁判になれば、最終的に裁判所が医学的根拠などをもとにして症状固定日を判断します。
(3) そのため、保険会社から「そろそろ症状固定してください」と言われたとしても、医師と相談し、必要であれば治療を継続することが必要です。
被害者自身が納得できる時期を症状固定日とすることが重要です。
具体的には、医師が作成する自賠責後遺障害診断書の「症状固定日」が、原則として症状固定日となります。
(4) 保険会社から治療費の支払いを打ち切られたとしても、これをもって症状固定日となるのではありません。
(5) 保険会社から治療費の支払いを打ち切られた後は、一旦自費で通院し、症状固定日までの損害を算定して請求することになります。
もっとも、一旦自費で通院することになるため、被害者自身において十分にご理解頂くことは必要になります。
4 症状固定について弁護士ができること
症状固定について弁護士ができることは多岐にわたります。
主なものは次のとおりです。
(1) 症状固定時期のアドバイス
保険会社から被害者に対し、早すぎる時期に症状固定を告げられた場合、その時期が適切であるかについて医療記録を精査し、必要であれば、医療照会や医師面談などを行って、症状固定時期を争うことができます。
これにより、適切な時期まで治療を継続するよう促し、早期の治療打ち切りを修正します。
(2) 医療機関・主治医との連携
医師に対し、診断書や後遺障害診断書の記載内容について具体的に依頼することができます。
せっかく診断書や後遺障害診断書を作成頂いても、その記載内容が損害の証明に不十分な場合は、補充の意見書や追記の依頼をします。但し、最終的に医学的判断にかかわる部分は、医師の判断に従うことになります。
(3) 後遺障害等級認定のサポート
症状固定後は、自賠責の後遺障害等級認定手続きに移行しますが、その申請資料の収集・精査をサポートします。
特に「被害者請求方式」での申請を選ぶ場合は、必要資料の取り寄せ・書面作成・医証の収集を通じて、等級認定を有利に導くことが可能です。
(4) 症状固定時点までの損害の算定
医療費、通院交通費、休業損害など、症状固定までの損害額を適切に算定・請求します。
保険会社との交渉・訴訟対応も行うことができます。
(5) 不服申立て(異議申立て)
後遺障害等級が想定より低かった、あるいは非該当となった場合は、異議申立てを準備・代理することができます。その際、医師の意見書、追加の画像資料(MRI等)などを取り寄せて提出することが可能です。
(6) 弁護士の関与が特に有効な場面は次のとおりです。
- ① 保険会社が治療費の支払を早期に打ち切ろうとする場合
- ② 認定されるべき後遺障害等級が軽く見積もられている疑いがある場合
- ③ 被害者が症状の主観的な訴えしかできず、他覚的所見との整合性に課題がある場合
- ④ 精神的な後遺症(PTSDや高次脳機能障害など)の主張が必要な場合
まずは、当事務所にご相談ください。








