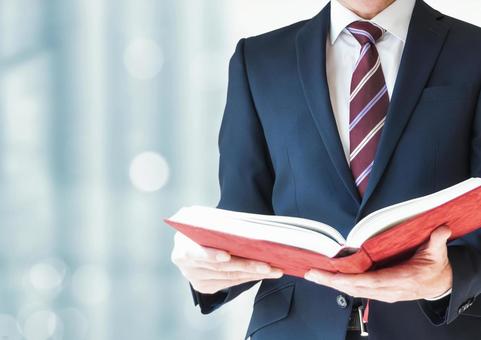1 高次脳機能障害の症状
高次脳機能障害とは、交通事故などを原因とする脳の損傷により認知機能や社会適応能力が低下する障害です。
主な症状として、次のものがあげられます。
- ① 記憶障害(新しいことを覚えられない)
- ② 注意障害(集中力が続かない)
- ③ 遂行機能障害(計画を立てたり臨機応変に対応できない)
- ④ 社会的行動障害(感情のコントロールが難しくなり、怒りっぽくなる、衝動的な行動をとる)
などがあります。
外見上の異常が少ないため、周囲から理解されにくく、職場復帰や対人関係のトラブルにつながることもあります。診断には神経心理学的検査が用いられ、適切なリハビリが必要です。
交通事故の損害賠償請求では後遺障害等級の認定が重要であり、医学的証拠を適切に収集することが求められます。
2 高次脳機能障害の治療の流れ
高次脳機能障害の治療は、発症の急性期から社会復帰まで段階的に進められます。
(1) 急性期(発症直後〜数週間)
交通事故などで脳に損傷を受けた直後は、生命維持と脳の回復を最優先します。集中治療室(ICU)での管理や、手術・薬物治療が行われることがあります。
この時期は意識障害が見られることも多く、回復の程度を慎重に観察します。
(2) 回復期(数週間〜数か月)
症状が安定したら、専門的なリハビリを開始します。
理学療法(身体機能の回復)、作業療法(手先の動きや日常動作の訓練)、言語療法(言語・コミュニケーション能力の回復)などを組み合わせ、認知機能や社会適応能力の回復を目指します。
(3) 社会復帰期(数か月〜数年)
退院後も通院リハビリや在宅リハビリを継続しながら、復職や日常生活の適応訓練を行います。
職場復帰が難しい場合は、職業訓練や就労支援を活用することもあります。
また、家族へのサポートやカウンセリングも重要です。
治療には時間がかかることが多く、本人だけでなく家族や周囲の理解と支援が不可欠です。適切な診断とリハビリ計画を立てることが、より良い回復への鍵となります。
3 高次脳機能障害の後遺障害認定について
(1) 交通事故による高次脳機能障害は、後遺障害等級認定の対象となります。
後遺障害等級とは、自賠責保険において後遺症の程度を評価し、適正な賠償額を決定する基準です。
高次脳機能障害は、認知機能の低下や社会適応能力の喪失が日常生活や労働にどの程度影響を与えるかに基づき、以下の等級が認定されることが一般的です。
主な等級と認定基準は次のとおりです。
1級1号(要介護) 「常時介護が必要な状態」
自分で食事や排泄ができず、意思疎通も困難
自賠責保険金額4000万円
2級1号(要介護) 「随時介護が必要な状態」(介助なしでは日常生活が困難)
記憶障害や注意障害が著しく、社会生活が送れない
自賠責保険金額3000万円
3級3号 「終身労務に服することができない」
労働がほぼ不可能だが、日常生活の一部は自立可能
自賠責保険金額2219万円
5級2号 「特に軽易な労務以外の労務に服することができない」
仕事ができても単純作業に限られる
自賠責保険金額1574万円
7級4号 「軽易な労務以外の労務に服することができない」
就労には支障があるが、一部の業務は可能
自賠責保険金額1051万円
(2) 認定のためのポイント
自賠責保険は、高次脳機能障害を認定する上で、次のような基準を満たす必要があるといわれています。
- ア 事故後の意識障害
- イ CT・MRIなどの画像所見
- ウ 症状の一貫性
以下、順次ご説明します。
ア 事故後の意識障害
自賠責は事故後の意識障害を重視しています。まず、初診の病院に確認します。
意識障害がなければ事故による高次脳機能障害とは認めないというわけではありませんが、意識障害があったのであればきちんと証明する必要があります。
初診の病院にかかるまで時間を要したために意識が回復していたという場合には、消防局に照会するなどして、救急車の出動記録を取り寄せて事故現場での意識障害の有無を確認することが重要です。
イ CT・MRIなどの画像所見
自賠責が重視しているのが画像所見であり、特に事故直後の画像を重視しています。
脳の画像にはCTとMRIがありますが、事故直後にCTは撮影されていても、MRIは撮影されていないということが時々あります。そのため、できるだけ早期にMRIを撮影することが重要です。
また、事故直後のCT・MRIで脳損傷が確認できない場合でも、3~6ヶ月後に脳の萎縮が見られることがありますので、3~6か月後に改めてCT・MRIを撮影することが必要です。
その場合,事故直後と比較する必要があるので,事故直後に撮影した断面と同じ断面について,事故直後に撮影した画像と同種類の画像を撮影する必要があります。
CT・MRIで異常がない場合、脳波、PET、SPECTなどの画像所見で異常があったとしても、自賠責保険は高次脳機能障害とは認めない傾向にあります。
このような場合には、裁判所で認定してもらうしかありません。
ウ 症状の一貫性
事故直後の症状が最も重いはずであるというのが自賠責の考え方です。
したがって、事故直後に症状がなかったにもかかわらず数か月後に症状が現れたという場合や、事故直後の症状よりも顕著に重症化したという場合、症状の原因が事故以外である可能性があるとして、事故による高次脳機能障害であると認めないことがあります。
もっとも、高次脳機能障害は、自分が異常であると自覚しにくいことがありますし、周囲が気づかないということもありますので、自分も周囲も気づかなかっただけで実際には症状は事故後から出現していたということもありえます。
このような場合には、その事実を証明していく必要があります。
以上の前提要件を満たした場合に、症状の程度によって具体的な後遺障害等級が判断されます。
(3) 適切な等級認定を受けるには、医学的な証拠の収集と専門家(弁護士や後遺障害認定に詳しい医師)の関与が重要です。認定された等級により、賠償額が大きく変わるため、慎重な対応が求められます。
4 高次脳機能障害での賠償の種類について
交通事故により高次脳機能障害を負った場合、被害者は加害者や保険会社に対して適正な損害賠償を請求できます。主な賠償項目は以下のとおりです。
(1) 治療関係費
入院・通院費:診察料、検査費、投薬費、リハビリ費用などです。
(2) 付添看護費
家族の付き添いが必要な場合の費用です。
(3) 将来の治療費
将来に向かって長期間のリハビリが必要な場合には、将来の医療費も請求可能です。
(4) 休業損害
事故により働けなくなった期間の収入補償です。
会社員は給与、個人事業主は事故前の収入を基に算出します。
(5) 入通院慰謝料
事故により入院通院による治療を余儀なくされたことに対する慰謝料です。
(6) 後遺障害慰謝料
入通院治療を行ったにもかかわらず、高次脳機能障害の後遺障害が残ったことに対する後遺障害等級に応じた慰謝料です。
(参考)裁判基準の例
1級の場合 2800万円
2級の場合 2370万円
3級の場合 1990万円
5級の場合 1400万円
7級の場合 1000万円
(7) 逸失利益(将来の収入減少分)
労働能力の喪失による減収を補償するものです。
事故前の収入と後遺障害等級による労働能力喪失率を基に計算します。
(参考)労働能力喪失率
1級の場合 100%
2級の場合 100%
3級の場合 100%
5級の場合 79%
7級の場合 56%
(8) 将来の介護費用(重度の場合)
常時または定期的な介護が必要な場合の費用です。
家族介護の場合でも一定額の賠償が認められることがあります。
(9) その他の費用
次の費用が認められる場合があります。
- ア 住宅改修費(バリアフリー化)
- イ 特殊車両購入費(車いす対応車など)
- ウ 介護用品費(車いす、介護ベッドなど)
高次脳機能障害の賠償請求は複雑であり、適切な後遺障害等級の認定と証拠収集が重要です。専門の弁護士に相談することで、適正な賠償を受けやすくなります。
5 高次脳機能障害となった際の対応の流れ
高次脳機能障害は発症後の対応が重要であり、適切な手続きを進めることで適正な治療や補償を受けることができます。以下の流れで対応することが一般的です。
(1) 急性期(発症直後~入院中)
- ① 医療機関での治療・診断を受ける
- ② 脳損傷の有無を確認するため、MRI・CT検査を実施
- ③ 意識障害の程度や脳の損傷部位を確認
- ④ 家族が経過を記録する
- ⑤ 記憶障害・注意障害・感情変化などの症状を記録し、後の診断や賠償請求の証拠とする
(2) 回復期(リハビリ開始)
- ① 専門医による診断・リハビリの開始
- ② 作業療法・理学療法・言語療法などを受ける
- ③ 神経心理学的検査(WAIS-Ⅳ、WMS-Rなど)を受け、認知機能の評価を行う
後遺障害等級認定の準備
(3) 後遺障害等級認定の申請
- ① 申請書類の準備
- ② 医師の診断書、画像検査結果、リハビリ記録、日常生活の支障に関する証拠(家族の陳述書など)
- ③ 後遺障害認定の申請(自賠責保険会社へ提出)
- ④ 後遺障害診断書をもとに審査が行われ、等級が決定
(4) 結果に不服がある場合は異議申立てを検討
必要に応じて追加の医学的証拠を提出し、異議申立てを行う
(5) 損害賠償請求(示談交渉・訴訟)
- ① 保険会社との示談交渉
- ② 休業損害、逸失利益、慰謝料などの請求を行う
(6) 示談不成立の場合は訴訟を提起する
- ① 後遺障害の程度に争いがある場合や、適正な賠償を受けられない場合は裁判へ
(7) 社会復帰・支援制度の活用
- ① 障害者手帳の申請(等級に応じて福祉サービスを受けられる)
- ② 障害年金の申請(一定の等級に該当すれば受給可能)
- ③ 就労支援の活用(職業リハビリや福祉サービスを利用)
特に後遺障害認定や損害賠償請求では、医学的証拠を適切に揃え、弁護士のサポートを受けることで、適正な補償を得られる可能性が高まります。
6 弁護士ができること
高次脳機能障害は、外見上の異常が少なく、周囲から理解されにくいため、適正な後遺障害認定や賠償を受けるには専門的な対応が必要です。弁護士は以下のようなサポートを提供できます。
(1) 適正な後遺障害等級認定のサポート
医療機関の選定・受診のアドバイス
高次脳機能障害に詳しい専門医の紹介
精密な神経心理学的検査(WAIS-Ⅳ、WMS-Rなど)の実施サポート
(2) 後遺障害認定に必要な証拠の収集
(3) 診断書の作成支援(医師と連携し、適正な診断書を取得)
(4) 家族による日常生活報告書の作成支援(症状を正確に伝えるためのアドバイス)
(5) リハビリ記録や職場の評価資料の収集
(6) 異議申立ての対応
低い等級に認定された場合、追加の医学的証拠を提出し、再審査を求める
(7) 適正な損害賠償請求の支援
賠償金の適正な計算と請求
休業損害、逸失利益、介護費用、慰謝料などの計算
(8) 保険会社が提示する低額の示談金を精査し、適正額を主張
(9) 示談交渉の代理
保険会社との交渉を代行し、被害者に有利な条件を引き出す
(10) 示談で解決しない場合、損害賠償請求訴訟を提起
医療記録や専門家意見を活用し、裁判で適正な賠償を求める
弁護士は、後遺障害認定のサポート、損害賠償請求の代理、社会復帰の支援を通じて、被害者とその家族をサポートします。特に適正な等級認定と賠償金の確保が重要であり、弁護士の専門的な知識と交渉力が大きな助けになります。
7 まずは弁護士にご相談ください
高次脳機能障害は、医学的証拠の収集や保険会社との交渉が難しく、適正な賠償を得るには専門的な知識が必要です。
弁護士に相談することで、後遺障害等級の適正な認定、十分な損害賠償の確保、被害者と家族の負担軽減を実現できます。特に保険会社との交渉や裁判対応を有利に進めるため、早めの相談が重要です。
まずは、当事務所にご相談ください。