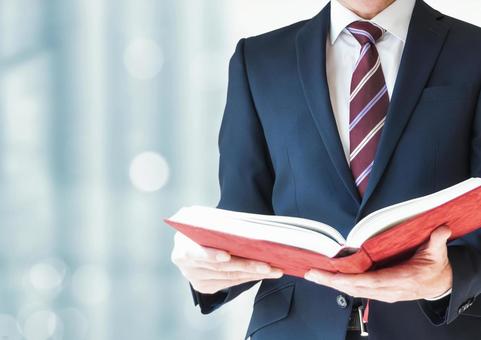1 交通事故でご家族を亡くされた方へ
突然の交通事故でご家族を亡くされ、ご遺族として不安なことばかりだと思います。
当事務所は、ご遺族の代理人として、ご遺族の精神的な負担を軽減しながら、加害者や保険会社との間に立って話し合いを進め、必要な場合は訴訟を提起し、適正な賠償額を請求します。
2 当事務所の損害賠償事例
- (1) 被害者(50代女性・家事従事者)は、自動車に同乗していたところ、対向車がセンターラインをはみ出してきたため、被害者が同乗していた車両と正面衝突し、被害者は、事故により頭蓋底骨折を負い、その後亡くなりました。
慰謝料と逸失利益を含む約5100万円が認められました。 - (2) 被害者(50代男性、運送業・自営)は、対面の歩行者信号が赤色の状態で横断歩道を歩行していたところ、左方から青色信号で走行してきた加害者の運転する車と衝突しました。被害者は、衝突による外傷性大動脈損傷および出血性ショックが原因で死亡しました。
訴訟提起して被害者の現実の稼働状況を立証することにより、申告所得を上回る休業損害及び逸失利益を含む合計約5000万円が認められました。 - (3) 被害者(30代男性、当時アルバイト)が自転車で車道の左端を走行していたところ、同車道を車で走行していた加害者が、突然道路左方の駐車場に向かって左折したため被害者に衝突しました。被害者は車の下敷きとなり亡くなりました。
訴訟提起して立証した結果、被害者の過失を0%とし、正社員になることを考慮して逸失利益を算定して約8300万円が認められました。 - (4) 被害者(50代男性、会社員)が自転車を運転して非優先道路を走行し、信号機による交通整理が行われていない交差点に進入したところ、右側の優先道路から進行してきた自動車に衝突されました。事故により、被害者は「びまん性脳損傷、外傷性くも膜下出血、頭蓋底骨折、肺挫傷、出血性ショック」により約5時間後に亡くなりました。
裁判所は、約4000万円に逸失利益を認定し、過失相殺後の損害額約5000万円にて和解が成立しました。
3 死亡事故の手続きの流れ
死亡事故が発生した場合の主な手続の流れは次のとおりです。
- (1) 交通事故で死亡事故が発生した場合、まず警察へ通報し、事故現場の保存を行います。
- (2) 警察は実況見分を行い、加害者または目撃者等について供述調書を作成します。
- (3) ご遺族は死亡診断書を受け取り、役所で死亡届を提出します。
- (4) 加害者は刑事責任(業務上過失致死罪等)や行政処分(免許取消等)の対象となります。
- (5) 加害者は、民事責任として遺族へ損害賠償義務を負います。
- (6) 民事上の損害賠償として、ご遺族から加害者に対し、慰謝料、逸失利益などを請求します。
4 死亡慰謝料について
被害者本人および近親者の精神的苦痛に対する賠償です。
死亡慰謝料は、被害者の年齢や家族構成などによって変わりますが、裁判基準では次のとおりです。
一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2500万円
その他 2000万円
慰謝料は事故状況によっても変わります。加害者側に重大な過失があった場合、飲酒運転、無免許運転をしていた場合などは、慰謝料が増額される可能性もあります。
5 死亡逸失利益について
(1)逸失利益(被害者が生存していれば得られたはずの収入)
基礎となる収入は、被害者の年齢、職業、収入を考慮して算出します。主婦の場合も家事労働の経済的価値が認められます。
生活費控除(被害者が生存していれば消費したであろう生活費)が差し引かれます。
通常67歳までを就労可能年数として計算します。
逸失利益の計算式は次のとおりです。
「基礎となる収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数×ライプニッツ係数」
6 弁護士ができること
交通死亡事故において、被害者(亡くなった方)の遺族を代理する弁護士ができることは非常に多岐にわたります。
主なものは次のとおりです。
(1) 損害賠償額の算定
被害者側弁護士の最も重要な役割の一つは、加害者またはその保険会社に対して損害賠償を請求することです。
- ① 死亡慰謝料(被害者及び遺族の精神的苦痛に対する損害)
- ② 死亡逸失利益(被害者が生きていれば得られたであろう収入)
- ③ 葬儀費用
- ④ その他実費(通院費、付き添い費、交通費 など)
などを適正に計算し、交渉または訴訟を通じて適正な損害賠償を請求します。
(2)示談交渉の代理
相手方保険会社や加害者と直接やり取りをせずに済むように、弁護士が代理人として示談交渉を行い、適正な損害額を請求します。
(3)訴訟提起
示談により解決ができない場合には、民事訴訟を提起します。
裁判所にて、損害を主張・立証し、適正な損害賠償を請求します。
(4) 刑事手続きへの関与
加害者が刑事責任を問われる場合(過失運転致死など)、遺族は「被害者参加制度」などを通じて、次のような手続に関与できます。
- ① 被害者参加制度の申立て
- ② 意見陳述(加害者の刑事裁判で遺族の意見を述べる)
- ③ 量刑についての意見提出
- ④ 刑事裁判の同行・説明
などを行い、遺族の想いが裁判所に伝わるようサポートします。
(5) 精神的サポートと相談対応
法律の面だけでなく、事故後の混乱や精神的ショックを受けている遺族の相談相手として、冷静なアドバイスを提供することもあります。
まずは、当事務所にご相談ください。