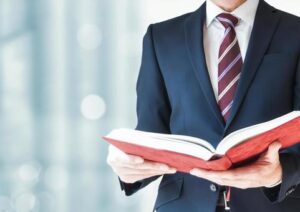-
後遺障害認定でお困りの方へ
 1 後遺障害とは
後遺障害とは、交通事故などによって傷病を受け、治療後も事故前の状態にまで完全に回復せず、不具合として後遺症が残ってしまうことがあります。
交通事故においては、交通事故によって生じてしまった後遺症のうち、自動車損害賠償保障法に基づく「後遺障害等級」のいずれかに該当したものを「後遺障害」といいます。
2 後遺障害の等級認定について
(1) 後遺障害等級は、損害保険料率算出機構という審査機関で審査され、基準を満たすときには、後遺障害等級の認定がなされます。
(2) 後遺障害は、その症状の重さに応じて1級から14級までの等級が定められています。
この等級のことを後遺…
2025.06.24
ケガ・治療損害賠償・保障
続きを見る »
1 後遺障害とは
後遺障害とは、交通事故などによって傷病を受け、治療後も事故前の状態にまで完全に回復せず、不具合として後遺症が残ってしまうことがあります。
交通事故においては、交通事故によって生じてしまった後遺症のうち、自動車損害賠償保障法に基づく「後遺障害等級」のいずれかに該当したものを「後遺障害」といいます。
2 後遺障害の等級認定について
(1) 後遺障害等級は、損害保険料率算出機構という審査機関で審査され、基準を満たすときには、後遺障害等級の認定がなされます。
(2) 後遺障害は、その症状の重さに応じて1級から14級までの等級が定められています。
この等級のことを後遺…
2025.06.24
ケガ・治療損害賠償・保障
続きを見る »
-
症状固定でお悩みの方へ
 1 症状固定とは?
(1) 交通事故による損害として認められる治療関係費は、原則として「症状固定日」までの各費用をいいます。
交通事故では、損害賠償額を算定する上で、重要なキーワードです。
(2) 症状固定とは、「これ以上治療しても症状が改善しない、もとの状態に戻らない」状態を言います。
(3) むちうち症を例にすると、病院で投薬やリハビリを受けると少しよくなるけれど、少し経つとまた戻り、という一進一退を繰り返す状態が症状固定です。
2 症状固定時期と賠償額の関係について
(1) 症状固定により治療期間は終了します。
原則として、症状固定日までの医療関係費が事故による損害…
2025.06.23
ケガ・治療損害賠償・保障弁護士保険
続きを見る »
1 症状固定とは?
(1) 交通事故による損害として認められる治療関係費は、原則として「症状固定日」までの各費用をいいます。
交通事故では、損害賠償額を算定する上で、重要なキーワードです。
(2) 症状固定とは、「これ以上治療しても症状が改善しない、もとの状態に戻らない」状態を言います。
(3) むちうち症を例にすると、病院で投薬やリハビリを受けると少しよくなるけれど、少し経つとまた戻り、という一進一退を繰り返す状態が症状固定です。
2 症状固定時期と賠償額の関係について
(1) 症状固定により治療期間は終了します。
原則として、症状固定日までの医療関係費が事故による損害…
2025.06.23
ケガ・治療損害賠償・保障弁護士保険
続きを見る »
-
交通事故で骨折された方へ
 1 交通事故で骨折をした際にまずすべきこと
(1) 医療機関での受診します(できるだけ早期の診断が重要です)
① すぐに病院へ行き、精密検査を受けます。
② レントゲン、CT、MRIなどで骨折の有無を確認します。
③ 痛みが軽くても、小さな骨折やヒビが入っている可能性があるため受診が必要です。
④ 医師に診断書を作成してもらい、骨折の部位・治療方針を明確にする。
診断書は、損害賠償請求や後遺障害認定に必要となります。
(2) 保険会社への連絡
① ご自身が加入している保険会社に事故を報告します。
治療費や休業補償の請求手続きを進めるために必要となりま…
2025.06.23
弁護士保険ケガ・治療
続きを見る »
1 交通事故で骨折をした際にまずすべきこと
(1) 医療機関での受診します(できるだけ早期の診断が重要です)
① すぐに病院へ行き、精密検査を受けます。
② レントゲン、CT、MRIなどで骨折の有無を確認します。
③ 痛みが軽くても、小さな骨折やヒビが入っている可能性があるため受診が必要です。
④ 医師に診断書を作成してもらい、骨折の部位・治療方針を明確にする。
診断書は、損害賠償請求や後遺障害認定に必要となります。
(2) 保険会社への連絡
① ご自身が加入している保険会社に事故を報告します。
治療費や休業補償の請求手続きを進めるために必要となりま…
2025.06.23
弁護士保険ケガ・治療
続きを見る »
-
高次脳機能障害についてお困りの方へ
 1 高次脳機能障害の症状
高次脳機能障害とは、交通事故などを原因とする脳の損傷により認知機能や社会適応能力が低下する障害です。
主な症状として、次のものがあげられます。
① 記憶障害(新しいことを覚えられない)
② 注意障害(集中力が続かない)
③ 遂行機能障害(計画を立てたり臨機応変に対応できない)
④ 社会的行動障害(感情のコントロールが難しくなり、怒りっぽくなる、衝動的な行動をとる)
などがあります。
外見上の異常が少ないため、周囲から理解されにくく、職場復帰や対人関係のトラブルにつながることもあります。診断には神経心理学的検査が用いられ、適切なリ…
2025.06.23
損害賠償・保障ケガ・治療
続きを見る »
1 高次脳機能障害の症状
高次脳機能障害とは、交通事故などを原因とする脳の損傷により認知機能や社会適応能力が低下する障害です。
主な症状として、次のものがあげられます。
① 記憶障害(新しいことを覚えられない)
② 注意障害(集中力が続かない)
③ 遂行機能障害(計画を立てたり臨機応変に対応できない)
④ 社会的行動障害(感情のコントロールが難しくなり、怒りっぽくなる、衝動的な行動をとる)
などがあります。
外見上の異常が少ないため、周囲から理解されにくく、職場復帰や対人関係のトラブルにつながることもあります。診断には神経心理学的検査が用いられ、適切なリ…
2025.06.23
損害賠償・保障ケガ・治療
続きを見る »
-
脊髄損傷でお困りの方へ
 1 脊椎損傷の症状
脊髄損傷は、脊椎の骨折や脱臼によって脊髄が圧迫・損傷されることで発生し、損傷の部位や程度によって運動機能や感覚障害が生じます。
頚髄を損傷すると四肢麻痺、胸髄や腰髄を損傷すると下半身の麻痺が起こることが多くあります。
頚髄損傷は、特に高速走行中の自動車の衝突や転倒事故で発生する可能性が高いものです。
2 脊椎損傷の診断について
交通事故における「脊髄損傷」は、次のとおり診断されます。
(1) 画像所見
脊椎に骨折や脱臼がある場合には、レントゲン(単純XP)によって診断します。
脊椎だけでなく、脊髄の損傷が疑われる場合には、CTやMRIにより診断し…
2025.06.23
ケガ・治療
続きを見る »
1 脊椎損傷の症状
脊髄損傷は、脊椎の骨折や脱臼によって脊髄が圧迫・損傷されることで発生し、損傷の部位や程度によって運動機能や感覚障害が生じます。
頚髄を損傷すると四肢麻痺、胸髄や腰髄を損傷すると下半身の麻痺が起こることが多くあります。
頚髄損傷は、特に高速走行中の自動車の衝突や転倒事故で発生する可能性が高いものです。
2 脊椎損傷の診断について
交通事故における「脊髄損傷」は、次のとおり診断されます。
(1) 画像所見
脊椎に骨折や脱臼がある場合には、レントゲン(単純XP)によって診断します。
脊椎だけでなく、脊髄の損傷が疑われる場合には、CTやMRIにより診断し…
2025.06.23
ケガ・治療
続きを見る »
-
交通事故でご家族を亡くされた方へ
 1 交通事故でご家族を亡くされた方へ
突然の交通事故でご家族を亡くされ、ご遺族として不安なことばかりだと思います。
当事務所は、ご遺族の代理人として、ご遺族の精神的な負担を軽減しながら、加害者や保険会社との間に立って話し合いを進め、必要な場合は訴訟を提起し、適正な賠償額を請求します。
2 当事務所の損害賠償事例
(1) 被害者(50代女性・家事従事者)は、自動車に同乗していたところ、対向車がセンターラインをはみ出してきたため、被害者が同乗していた車両と正面衝突し、被害者は、事故により頭蓋底骨折を負い、その後亡くなりました。
慰謝料と逸失利益を含む約5100万円が認められまし…
2025.06.23
損害賠償・保障弁護士保険ケガ・治療
続きを見る »
1 交通事故でご家族を亡くされた方へ
突然の交通事故でご家族を亡くされ、ご遺族として不安なことばかりだと思います。
当事務所は、ご遺族の代理人として、ご遺族の精神的な負担を軽減しながら、加害者や保険会社との間に立って話し合いを進め、必要な場合は訴訟を提起し、適正な賠償額を請求します。
2 当事務所の損害賠償事例
(1) 被害者(50代女性・家事従事者)は、自動車に同乗していたところ、対向車がセンターラインをはみ出してきたため、被害者が同乗していた車両と正面衝突し、被害者は、事故により頭蓋底骨折を負い、その後亡くなりました。
慰謝料と逸失利益を含む約5100万円が認められまし…
2025.06.23
損害賠償・保障弁護士保険ケガ・治療
続きを見る »
-
事故に遭われた方へ
 1 交通事故に遭ったらまずすべきこと
まずは落ち着いて次の行動を取ってください。
(1) まず、ご自身の安全を確保することが最優先です。
危険な場所にいる場合には安全な場所に移動して下さい。
(2) 警察に連絡してください。
警察への通報は、道路交通法上義務とされています。
事故の大小にかかわらず、警察に通報しなければ事故証明書が発行されず、損害賠償請求や保険金請求が難しくなる可能性があります。
万一、事故の相手方が拒否したとしても、必ず警察に通報してください。
(3) 相手方の住所、氏名、連絡先、車両のナンバープレート、加入している保険会社の情報を確認してください。…
2025.06.22
損害賠償・保障弁護士保険ケガ・治療
続きを見る »
1 交通事故に遭ったらまずすべきこと
まずは落ち着いて次の行動を取ってください。
(1) まず、ご自身の安全を確保することが最優先です。
危険な場所にいる場合には安全な場所に移動して下さい。
(2) 警察に連絡してください。
警察への通報は、道路交通法上義務とされています。
事故の大小にかかわらず、警察に通報しなければ事故証明書が発行されず、損害賠償請求や保険金請求が難しくなる可能性があります。
万一、事故の相手方が拒否したとしても、必ず警察に通報してください。
(3) 相手方の住所、氏名、連絡先、車両のナンバープレート、加入している保険会社の情報を確認してください。…
2025.06.22
損害賠償・保障弁護士保険ケガ・治療
続きを見る »
熊田法律事務所 (福岡県弁護士会所属)地下鉄「赤坂駅」より徒歩5分